前回は「慎重に行うピットの配筋検査〜構造設計者がしっかりチェック・緻密に組み上げられた「作品のような」鉄筋・大事な意匠設計者と構造設計者の協業〜」の話でした。
ピット耐圧盤工事

配筋検査の指摘事項の対処が完了し、いよいよ最初のコンクリート打設になります。
まずは、最も下部の耐圧盤を打設します。
壁式鉄筋コンクリート造は、各部分の直方体の「直接基礎」を掘った地盤につくる方法が多いです。
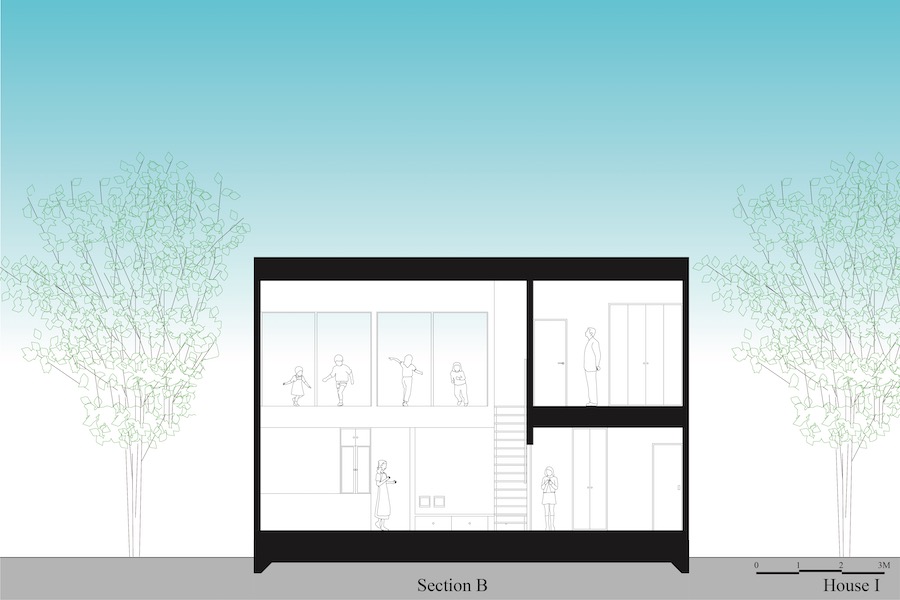
今回は木造個人邸の基礎と同様に、平たい耐圧盤を最下部に設置する構造にしました。
木造住宅は、昔は布基礎と呼ばれる工法が多かったですが、2000年頃から耐圧盤を施工する「ベタ基礎」が中心です。

建物の重量が遥かに軽い木造で「ベタ基礎」とするのは、構造的安定確保もありますが、湿気対策もあります。
ベタ基礎=コンクリート基礎は、地面と木造建築を完全に遮断します。
そして、地面から湿気が上がってきて、木造躯体を傷める可能性を大きく下げます。
安定感が高い耐圧盤と基礎のハイブリッド構造
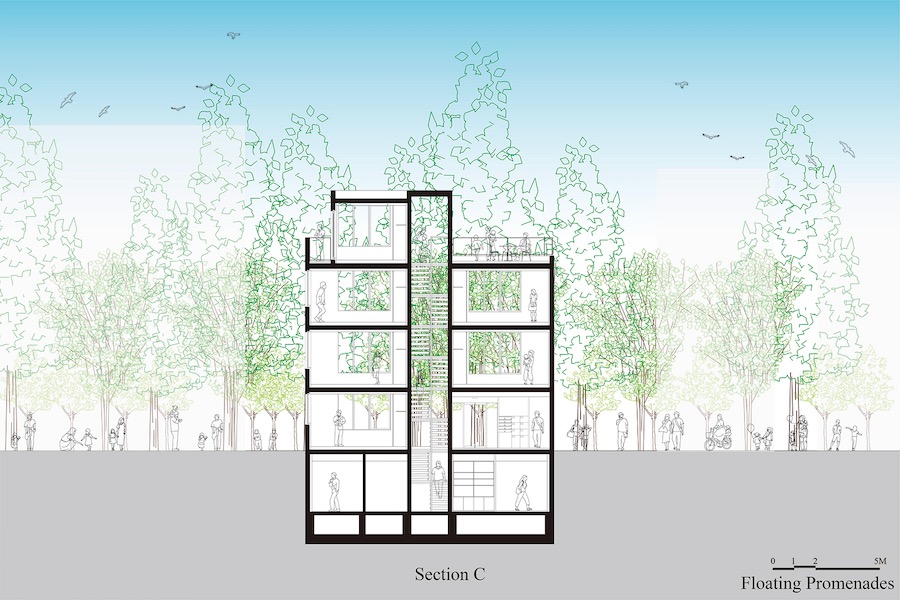
 Yoshitaka Uchino
Yoshitaka Uchino建物と同じ形状の平たい耐圧盤が、
下部の地面にしっかりと乗るので安定します。
地面に基礎を差し込むように設置して、構造を作りだす事が多い鉄筋コンクリート造。
最下面の耐圧盤は、全ての基礎を合体して、非常に堅牢な構造となります。
さらに、ピット周囲が鉄筋コンクリートで覆われるため、設備のメンテナンス性も向上します。
このように、耐圧盤を設置することは、多少のコストアップにつながりますが、



耐震性の向上と設備メンテナンス性の向上は、
コストアップを大きく上回ると考えます。



建築コストは非常に大事なので、
かけるところはかける姿勢が大事です。



合理的な設計をして、
総工事費は削減するようにします。
耐圧盤下部の断熱材施工


そして、断熱材を施工してゆきます。



時期によっては結露が発生しやすいので、
断熱材を、きちんと施工することがポイントですね。
今回は、地下は趣味のためのスペースとして使われます。
倉庫などのモノだけではなく、人が短期間でも居住するスペースなので、断熱材は非常に重要です。


分厚い断熱材がギッシリと満遍なく設置されてゆきます。
これで断熱性能はバッチリです。
地下は機械換気しますが、地上部分に比べて空気の流れは少なくなります。



時期によっては結露が発生しやすいので、
断熱材を、きちんと施工することがポイントですね。


公園の樹木が青々としてきた中、入念に工事が進められてゆきます。
次回は、ピットの配筋検査です。
次回は上記リンクです。
竣工写真は、下記サイトをご覧下さい。



