前回は「地盤面下を掘削する根切工事〜根切の言葉の由来・織田信長の天下統一戦・設備が集中するピット空間・捨てコンクリート打設・マンション工事のプロセス〜」の話でした。
建物を支える基礎配筋工事

捨てコンクリートを打設し、いよいよ基礎の配筋工事に入ります。
地面の上に立てる建物は、「地面に支えられる」存在です。
そして、建物とそこに住む人々や様々な物を含む巨大な重量(荷重)を地面に伝える役割が基礎です。
そのため、基礎は文字通り「最も重要な部分」となります。
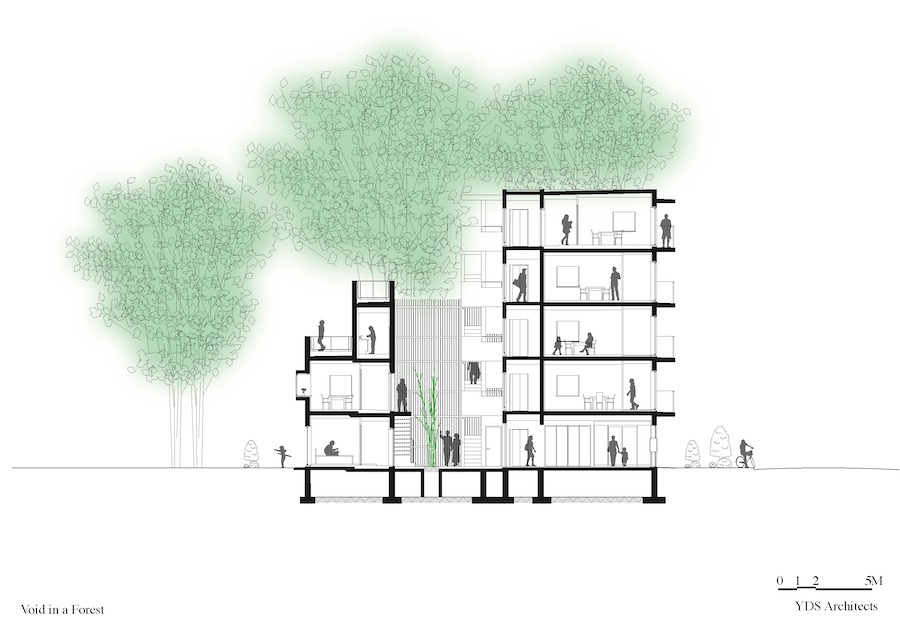

この頃から、現場は現場を管理するゼネコン職員・職人さんともに熱くなってきます。
基礎梁は、とても大きな梁で、高さは高校生〜大人の身長くらいのサイズがあります。
様々なサイズと種類の鉄筋を組み上げる配筋

そして鉄筋を組んで、基礎梁の配筋工事を進めるためには、足場が必要です。
まずは、そのための足場を作ってゆきます。
職人のみなさんが一生懸命足場を組み立ててゆき、足場ができてきました。
足場はスチールでできているため、とても頑丈ですが結構重いです。
普通の人が持ち運ぶには、ちょっと大変な重さです。
慣れている職人さんたちはどんどん運んで組み立てます。
いよいよ、基礎の配筋工事が進んでゆきます。

今回の建物は壁式鉄筋コンクリート造で、壁柱・梁の幅は220mmです。
中層の6階建てくらいの鉄筋コンクリートの柱の断面は、およそ700〜800mm角程度になります。
そして基礎梁の幅も800mm程度あることが多いので、それと比較すると非常に薄い基礎梁です。
基礎梁も厚さは薄いですが、高さは1500mmで結構大きいです。
これら基礎梁の鉄筋の種類は、鉄筋径(直径)が数種類あり、梁ごとに本数が異なります。

それらを「構造設計図書」という図面を元に、職人さんたちが丁寧に組み上げてゆきます。
十字にクロスする部分は、クロスする基礎梁の鉄筋に上下が出てきます。
そうした点にも注意してゆきながら、丁寧に組み上げてゆきます。
生き物のように感じられる鉄筋

太い鉄筋・細い鉄筋など様々あり、これらが組み上がってゆくと、
 Yoshitaka Uchino
Yoshitaka Uchinoまるで生き物のように
感じられます。
鉄筋同士を固定する(緊結する)部分には、細い紐状の針金を使って留めます。
この針金を職人さんたちが、特殊な工具を使ってクルクルっと回すと、動かないように固定されます。
細い針金ですが、試しに鉄筋を少し動かそうとしても、なかなか動きません。
「しっかりと固定されている」ことがわかります。
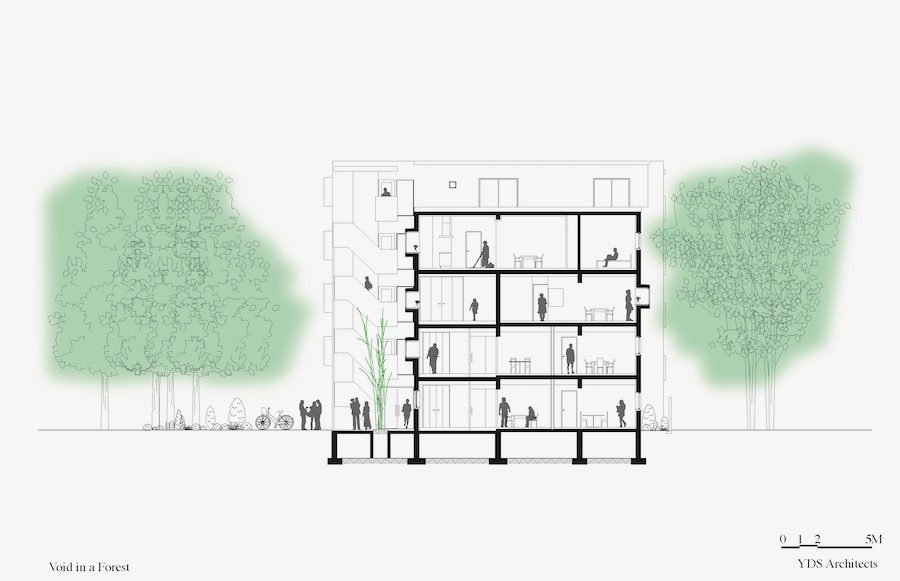
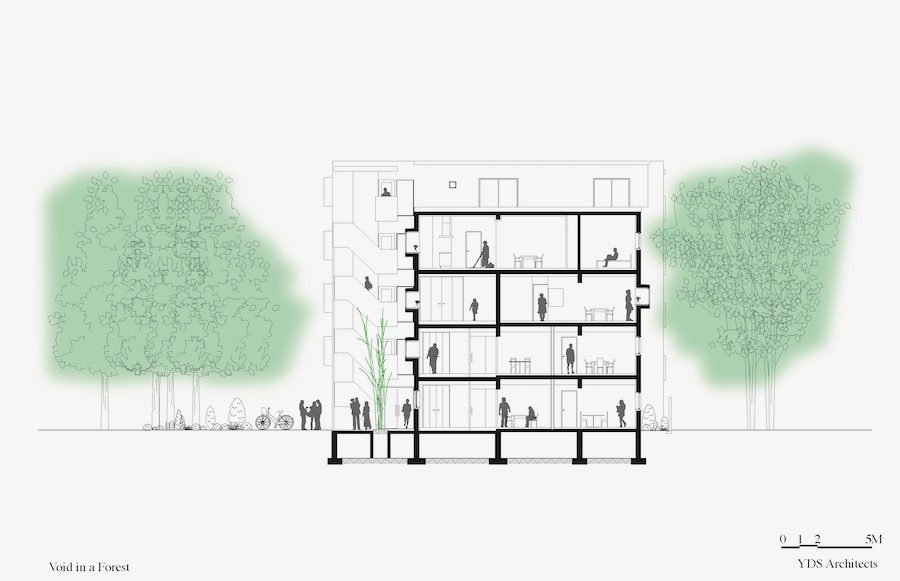
これから型枠を組んで、コンクリートを流し込んでゆきます。



コンクリート打設の際に、
鉄筋が動かないようにしっかり固定します。
次回は配筋検査です。
竣工写真は、下記サイトをご覧下さい。


