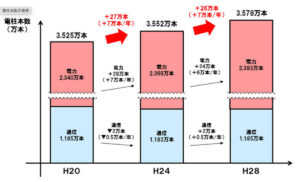前回は「美しい街づくりと電柱〜増加している日本の都市の電柱・建築の外観イメージを破壊する電柱と電線〜」の話でした。
景観や建築の外観を損ねる電柱と電線:電柱と電線による見栄えダウン

日本の街中には、電柱と電線が多数見受けられます。
電線には鳥たちが止まりやすいので、「鳥が止まるのを防ぐ」ための「鳥よけ」が付いていることもあります。
この場合、ただでさえ「景観に悪い」電線は「電線の存在が強調される」ことにつながり、
 Yoshitaka Uchino
Yoshitaka Uchino鳥よけによって、
黒い電線が強化され、景観を悪くします。
近年、東京などでは電線の地中化が進められていますが、進行は遅いです。
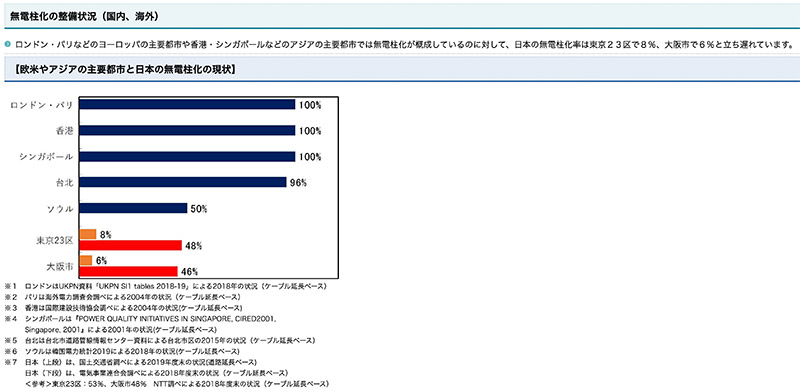
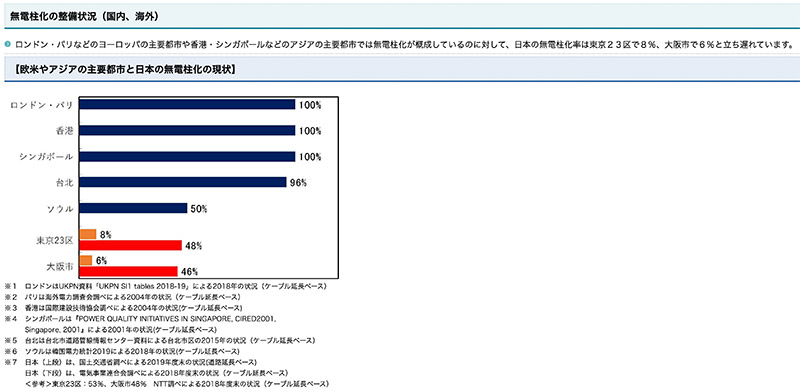
欧州の都市では、「電柱や電線がほとんどない」印象が強いですが、実は台北やソウルも無電柱化率が高いです。



東京や大阪の
「無電柱化率」の低さが際立っています。


都市に建築を設計する時、敷地周辺の状況を調査することが、設計者として極めて大事です。
設計着手前の現地調査に関する話を、上記リンクでご紹介しています。
現地調査の際には、道路や隣地の状況を細かくチェックし、周辺環境を念頭に入れて設計します。
その際、電柱のことは多少は気になりますが、大きな要素になることは少ないです。
そして、完成して竣工写真を撮影するときに、



「あの電柱や電線がなければ良いのに」と
思うことがあります。
「電柱や電線を考慮する設計」も考えられなくはないですが、それよりも重要なことが多数あります。
上の豊島の家は、商店街に建築されたこともあり、多数の電線が見えています。
このように、経過や建築の外観を大きく損ねるのが電柱と電線です。
「無電柱化」の強力推進と地震国日本における防災計画


ただでさえ、「景観に大ダメージを与える」電柱と電線ですが、上に柱上トランスが乗っていることがあります。
このトランスは、「高圧電流を家庭用などの低圧電流に変圧するため」の変圧器が入っています。
送電の効率を上げるためには、どうしても高圧にする必要があります。
そのため、発電所からは、かなり高い電圧が送られます。
そのため、「どうしても必要なもの」が柱状トランスですが、



電柱の上のトランスは、
誰が見ても醜い存在です。
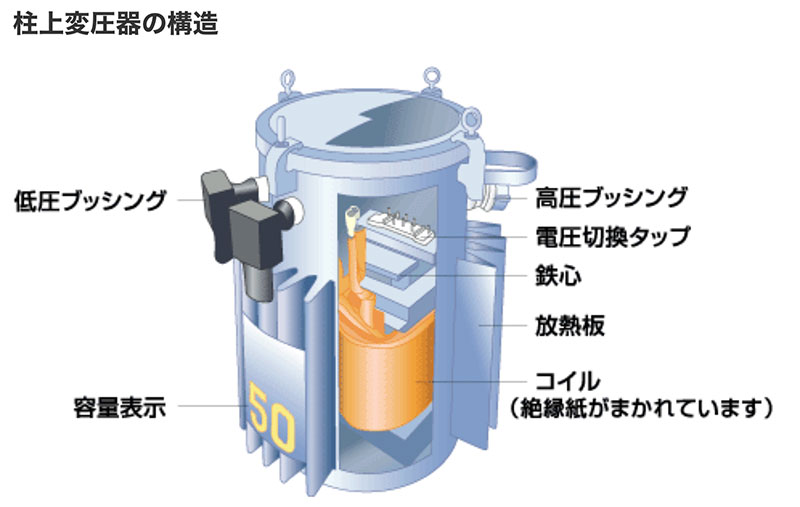
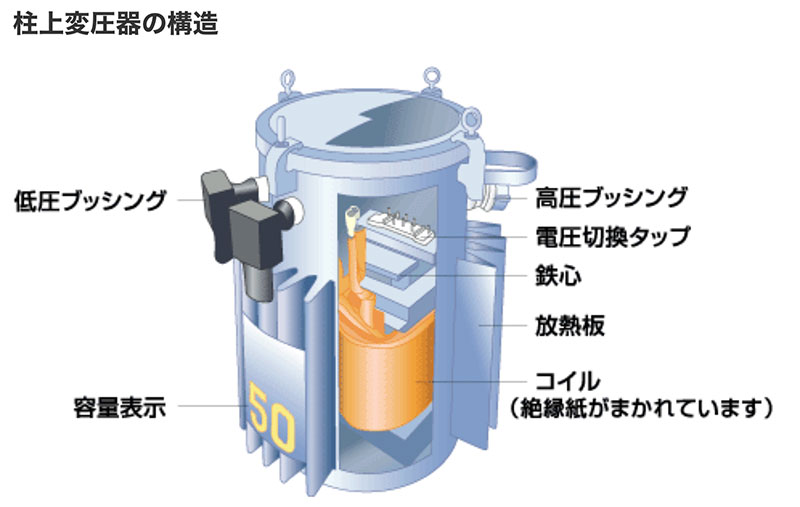
柱上トランスには様々な物が入っており、おそらくメーカーの方々は、



なんとか小さくする工夫を
したが、これが最小限・・・
出来るだけ小さく、軽量にするように考えて設計されているはずです。
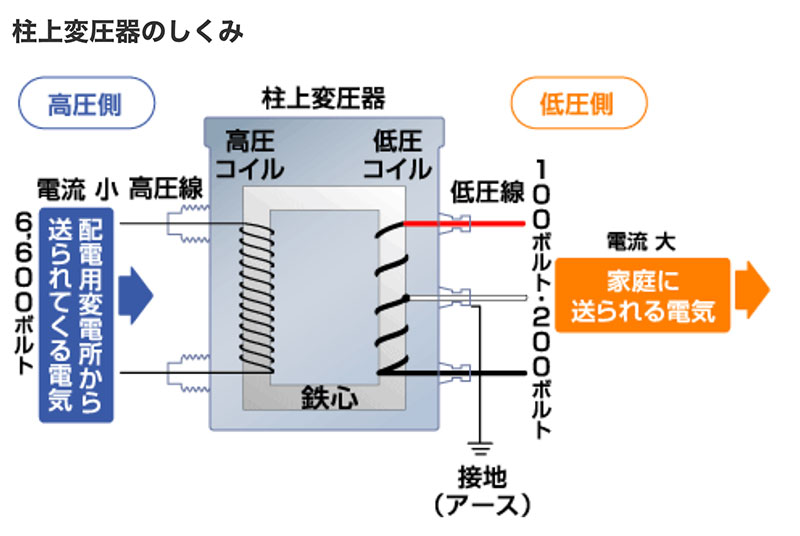
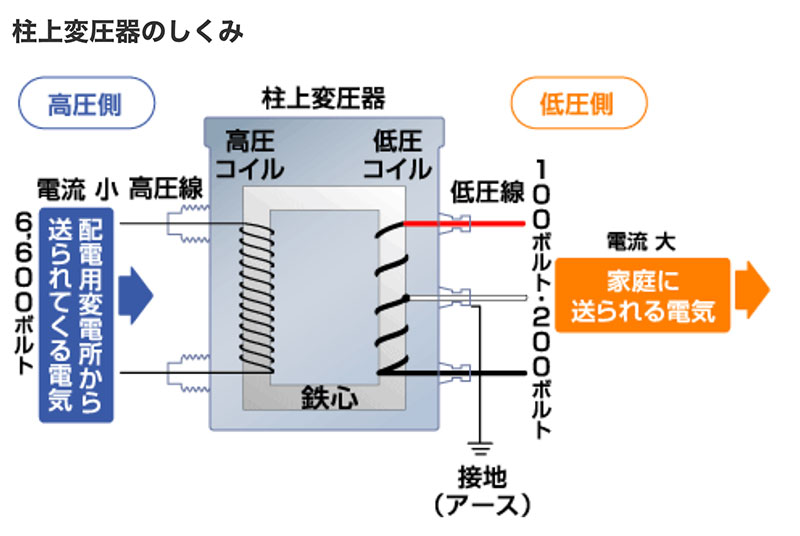
発電所や変電所からは6,600ボルトもの超高圧電流として送られてきます。
そして、それを柱状変圧器が100ボルト、200ボルトに変圧しています。
この意味では、「都市に不可欠な存在」が柱上トランスですが、



もう少し工夫して、
下部に設置して欲しいです。
無電柱化が進んでいるエリアでは、柱状トランスは路上の箱に収められていることが多いです。
電柱・電線も柱上トランスも、景観が悪いだけでなく、「落下したら危険」です。
| 年 | 地震名 |
| 1995 | 阪神淡路大震災 |
| 2011 | 東日本大震災 |
| 2016 | 熊本地震 |
| 2024 | 能登半島地震 |
「超地震国」とも言える日本では、近年大地震が頻発しています。
今年2025年は、阪神淡路大震災から、ちょうど30年です。


この阪神淡路大震災勃発のとき、筆者は高校2年生でしたが、あまりの惨事に「驚きを超えた」のを覚えています。
この後、2011年の東日本大震災があり、その後も熊本地震、能登半島地震と続いています。
この流れでゆくと、2030年頃までには少なくとも、熊本地震クラスの地震が起こる確率が高いです。
地震の際には、電柱・電線・柱上トランスは大変危険なので、早期に少なくする必要があります。
防災は、建築や土木で出来ることは限られているので、この「無電柱化」は強く推進すべきです。
官民あげて、「無電柱化の大プロジェクト」を推進して欲しいと思います。